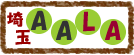緊急学習会[激動する中東情勢―『アラブの春』の現状と展望
民衆の長い運動の蓄積の上の「春」
運動は、「短期的には失敗もあるが、長期的には成功している」「市民は自分たちが物
事を変えることができることを知った。」「政府が国民の声を無視できなくなった。」
これらはいわゆる「アラブの春」と呼ばれるたたかいの、現在の到達点と言えるので
はないか。また、「アラブの春」をどう呼ぶかについても「いわゆる『アラブの春』、
革命、中東変動、アラブ変動、中東地殻変動、民主的変革を求める運動、アラブの蜂
起、政変、アラブの覚醒」など様々であるが、包括的な意味を込めてここでは取りあ
えず「アラブの春」を使用する。
  中東研究者の尾崎芙紀さんは、2010 年にチュニジアから始まった、アラブ諸国での
変革の運動について豊富な資料に基づき講演しました。講義はまず、アラブ人とは
「アラビア語を話し、文化的伝統を共有する者」、パレスチナ人とは「パレスチナ
に住む、或いはそこを追われたアラブ人とその子孫」等の定義からスタート。「アラ
ブの春」のたたかいは突然に起こったのではなく、この運動の基礎にそれまでの労働
運動、平和運動の蓄積があった。そして「アラブの春」以降多くのアラブ諸国では
総選挙が実施され、或いは今後実施予定で、憲法制定作業も進捗していること。また
モロッコ、オマーン、ヨルダン、バーレーンなどの王国では、国王の権限制限、憲
法裁判所の設置、議会の権限強化などが進められていること等が紹介されました。
講演後、6 人が質問をしました。「レバノンの状況はどうか?個人での入国は可能
か?」では「レバノン内戦後、シリアはレバノンから撤退しているが、シリアはレ
バノンを属国とみている。入国等についてはレバノン大学の教員が近く来日するの
で詳しく聞いて個別にお答えしたい。」「イランに対する制裁措置でイランはどう
いう状況か?」では「1979 年のイラン革命は非暴力であり、『アラブの春』の先
取りではなかったか。2009 年の大統領選挙の不正を追及した学生運動が弾圧された。
国民の生活は制裁措置で厳しい状況にある」「シリアで政権が続いているのはなぜ
か?」では「支持基盤はアラウィ派だけでなく、国内の一定の企業家等をも掌握し
ていることが政権の維持に繋がっている」「中東の女性の状況は?」では「長い歴
史の中で女性の地位が低いが、地位の向上を図ってきていること、イランでは女性
の地位は高いが、サウジでは女性の運転禁止などもある。」等々。講演はじっくり
学ぶ良い機会となりました。
中東研究者の尾崎芙紀さんは、2010 年にチュニジアから始まった、アラブ諸国での
変革の運動について豊富な資料に基づき講演しました。講義はまず、アラブ人とは
「アラビア語を話し、文化的伝統を共有する者」、パレスチナ人とは「パレスチナ
に住む、或いはそこを追われたアラブ人とその子孫」等の定義からスタート。「アラ
ブの春」のたたかいは突然に起こったのではなく、この運動の基礎にそれまでの労働
運動、平和運動の蓄積があった。そして「アラブの春」以降多くのアラブ諸国では
総選挙が実施され、或いは今後実施予定で、憲法制定作業も進捗していること。また
モロッコ、オマーン、ヨルダン、バーレーンなどの王国では、国王の権限制限、憲
法裁判所の設置、議会の権限強化などが進められていること等が紹介されました。
講演後、6 人が質問をしました。「レバノンの状況はどうか?個人での入国は可能
か?」では「レバノン内戦後、シリアはレバノンから撤退しているが、シリアはレ
バノンを属国とみている。入国等についてはレバノン大学の教員が近く来日するの
で詳しく聞いて個別にお答えしたい。」「イランに対する制裁措置でイランはどう
いう状況か?」では「1979 年のイラン革命は非暴力であり、『アラブの春』の先
取りではなかったか。2009 年の大統領選挙の不正を追及した学生運動が弾圧された。
国民の生活は制裁措置で厳しい状況にある」「シリアで政権が続いているのはなぜ
か?」では「支持基盤はアラウィ派だけでなく、国内の一定の企業家等をも掌握し
ていることが政権の維持に繋がっている」「中東の女性の状況は?」では「長い歴
史の中で女性の地位が低いが、地位の向上を図ってきていること、イランでは女性
の地位は高いが、サウジでは女性の運転禁止などもある。」等々。講演はじっくり
学ぶ良い機会となりました。
|